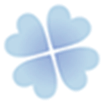看護部
看護部の理念・方針
患者さんが病院で過ごされるそのとき、傍らに寄り添い「安心できる看護」を実践していきます。そして、その方の暮らしをどう支援するかをともに考えて参ります。
-
看護部理念
皆様に心のこもった温かな看護・介護をお届けします
-
看護部方針
-
皆様に御満足いただける看護・介護をいたします。
-
確かな安全をお届けします
-
人と人・機能と機能をつなぎ、一人ひとりにあった支援をいたします。
-
互いを思いやる職場づくりを推し進めます。
-
「FEATURE教育インテリジェント賞」をいただきました。
ナイチンゲール生誕200年となる2020年、NURSING NOWは、看護職への関心を深め、地位を向上することを目的とした世界的なキャンペーンです。石川県看護協会もその一環としてキャンペーンを展開しました。
そしてこの度、浅ノ川グループ看護管理代表者会(浅ノ川総合病院、心臓血管センター金沢循環器病院、金沢脳神経外科病院、桜ヶ丘病院、千木病院・金沢看護専門学校)が2019年度に次世代看護管理者を育成する目的で半年にわたって研修を展開した功績が認められ、「FEATURE教育インテリジェント賞」をいただきました。

今後も次代を担う人材育成に努めます。
看護部内のご紹介
看護部長:柳 美知代

浅ノ川総合病院看護部では、『皆様に心のこもった温かな看護・介護をお届けします』を理念とし、来院される皆様に温もりのあるケアが提供できるよう日々研鑚を積み重ねながらスタッフ一丸となって看護提供を行っています。
また、専門性の高い看護師の育成にも力を入れており、認定看護師や特定行為研修を修了した看護師が毎年誕生し、それぞれの役割を活かすべくケアチームに所属しその力を発揮しています。このほか、社会や医療・看護を取り巻く情勢の変化に対応するために、次世代の看護管理者を育成する研修会を浅ノ川グループ全体で行い、新たに多くの看護管理者が誕生しています。看護管理の視点を持つスタッフが増えることは、私たちにとって大きな強みとなっています。
高齢化の進行と同時に、少子化による生産年齢人口の減少は、医療・介護の領域において深刻な課題となっています。これらの課題を解決するため、医療DXが進められ働く環境も変化しつつありますが、患者さんの傍らにいる看護職員ひとり一人の温もりのあるケアは機械化できないものが多いです。このような変化の中にあっても私たちが大切にしたいのは、患者さん・ご家族の思いに寄り添い、患者さん・ご家族の最善をともに考え、その人らしく生きることを支える看護を提供することです。働くスタッフみんなが互いを支え合い、笑顔で最大限の力を発揮し、患者さんの力になれるような病院作りに全力を注ぎたいと思っています。
副看護部長:東 良子

地域連携部門、地域包括、医療療養病棟を引き続き担当します。
少子高齢化に伴い、医療・介護サービスの提供を受ける人口に対して、サービスを提供する側の人材不足により需要と供給のアンバランスが起きています。また医療は入院から在宅へとシフトしており、治療を終えた患者がいかに円滑に、在宅また各施設への退院調整が実践できるか重要になります。円滑な退院調整に向けて多職種連携、退院支援看護師の人材育成などに取り組んでいきたいと考えています。
看護師として看護は自分自身を成長させ一生学び続けることができる素晴らしい職業だと思っています。
患者と共感する気持ちを大切に患者と直接向き合う事が出来、看護職員一人ひとり生き生きと仕事ができるように、また長く働き続けられる職場環境作りの支援に取り組んでいきます。
副看護部長:作田 憲一

急性期病棟、手術部、透析センター及び現任教育、臨床実習全般を担当しています。私はこれまで新人看護師や実地指導者の育成計画の立案や研修の実施、臨床指導や臨地実習の調整など教育に関して多く携わってきました。社会や医療現場は日々変化しています。その中で当院の看護師・介護福祉士、看護補助者が誇りをもって自らの役割を遂行できるように、医療DXやタスクシフト・シェアなどを踏まえた教育体制を整えていきます。
また、異なる価値観や考えをもつ人々と協働していく中で周囲から信頼され、礼節を重んじて行動できる人財の育成を目指し、個人のキャリアアップへの支援と共に地域の安心と健康に貢献できる次世代の看護師・介護福祉士の育成に努めて行きます。
看護部顧問:中瀬 美恵子

2024年4月からは、看護部顧問という組織をながめる事ができる立ち位置になりました。今後1年は看護部全体と病院・関連施設、社会の動向をよく俯瞰した上で、看護部の支援を目指していきます。
2019年度から開始した浅ノ川グループ看護管理者研修は、2024年度で5回目を迎えることとなりました。第4回まで延べ117名の修了生を輩出し、次のステージにステップアップするにあたり歴代受講生にアンケートをとり、各自の成長を実感しました。
改めてこの研修の理念「自走する看護集団」・目的「自己を変革し、自責の立場から行動できる人材を育成する」を再確認しました。また、この研修はマネジメントの基盤になるスキルを取得できるように構成した内容であり、研修名を「マネジメントベーシックスキル育成研修 For next Generation」と改名しております。更に現状のニーズにあったカリキュラムを再構築し、2024年度は、自己をメタ認知するためのリフレクションを教科目に組み入れスタートする予定となっております。どのような研修が提供できるのか楽しみです。
浅ノ川グループがよりスキルアップし盤石となるべく努力を重ねて参ります。どうぞよろしくお願いします。
教育理念と方針
認定看護師紹介
感染管理認定看護師

感染対策室 江波 麻貴
“笑顔だけは感染させよう!”をキャッチフレーズに2012年から、感染対策室専従看護師として活動しています。
院内の感染対策は、病院に出入りする全ての人々が対象です。あらゆる職種と協力し、啓発活動や職員教育、サーベイランスを実施することで様々な感染の早期発見・予防に努めています。
当院は、感染対策向上加算1を取得しています。連携施設と協働し、地域で感染対策を強化しています。
院内外からの「あれ?こういう時、どうするの?」や「この方法は正しいのかな?」、「もっと良い方法はないのかな?」等の疑問の声を常時受け付けております。患者さんやご家族の環境、施設の特性に応じた最善の方法を一緒に考えさせていただきます。
感染管理認定看護師

感染対策室 上島 雅子
2015年に感染管理認定看護師となりました。私は感染対策室と地域連携室を兼務しています。当院では、医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・管理栄養士・理学療法士で構成された感染対策チームで、それぞれの専門性を発揮し一緒に活動しています。更に看護師と介護福祉士で構成されるチームで、院内感染防止に向けて取り組んでいます。
「浅ノ川の底力」を職員みんなで発揮し、患者さんをはじめ職員や病院に出入りするすべての人々を感染から守れるよう病院の日常業務や病院内全般における院内感染防止など感染管理・感染対策の役割を果たして行きたいと思っています。
感染管理認定看護師

感染対策室 坂本 信彰
2015年に感染管理認定看護師になりました坂本です!感染管理・制御のAIを開発して、だれでもどこでも感染を制御できるような世の中をつくることを夢に抱く坂本です!
私は、感染対策室の専従看護師として病院内の感染対策を補完しつつ、感染対策に関わる地域連携(病院・クリニック・高齢者福祉施設等)の仕事をしています。
さて、世界において2050年には、抗菌薬(俗に言う、抗生物質)が効かない細菌(薬剤耐性菌)による死亡者数が、「がん」による死亡者数を上回ると言われています。病院の外でも、このような細菌が徐々に広がっています。今後起こりうる新型コロナウイルス感染症のような新興感染症への対策も大切ですが、病院内の感染対策だけでは、子供たちの未来を救えないかもしれません。そんな子供たちの未来のためにも、われわれ感染管理認定看護師は、ゆっくり・焦らず・バランスよく、院内外の感染対策を推進していきます。
感染管理認定看護師

手術部 森 隆平
感染管理認定看護師の役割は、疫学、微生物学、感染症学、消毒と滅菌、関係法規などに関する専門知識を基盤に、施設の状況にあった効果的な感染管理プログラムを構築し、病院に関わる全ての人を感染から守ることにあります。特にコロナ渦における感染管理認定看護師はその専門性を発揮し、当院に出入りする全ての関係者を感染から守るための活動を行ってきました。世間はwithコロナ、アフターコロナが話題になっていますが、まだまだ各医療機関における新型コロナウイルスの脅威は完全には消えていません。新型コロナウイルスだけではありませんが、われわれ感染管理認定看護師はこれからも変わらず院内感染対策を行っていきます。
感染管理認定看護師

病棟所属 泉屋 裕一
2023年に感染管理認定看護師となりました。一般病棟で兼任の感染管理認定看護師として勤務しています。当院は新型コロナウイルス感染症の発生当初から地域から求められる対応を行っています。私は関係部署と協力し、新型コロナウイルス感染症に対する実務を取りまとめてきました。「こんな時どうすれば?」「正しい方法は?」「想定外の場面での対応は?」といった問題を院内感染対策チームや現場の仲間と対応する中で、根拠に基づいた知識と技術を習得したいと考え感染管理認定看護師を取得しました。
感染対策は職員だけでなく患者さんとそのご家族、病院に関わる方の協力が必要です。患者さんの特性や、職員の所属する部署の専門性を理解し尊重しながら協力して行われます。今後、新型コロナウイルス感染症だけでなく、既存の病原微生物、発生が予想される新興感染症に対応する事が求められています。私は病棟で働く感染管理認定看護師、感染対策チームの一員として、現場で発生する問題に対して仲間と協力して実践、指導、相談を行えるよう活動していきたいと考えています。
がん性疼痛看護認定看護師

外来 加藤あゆみ
がんの痛みは診断時に約30%、進行がんでは約70%の人が体験すると言われています。
WHO(世界保健機構)は「がんの痛みは治療できる症状であり、治療すべき症状である」と宣言しており、痛みの治療は、がんの治療と平行して行っていく大切な治療です。
痛みは日常生活に影響を及ぼすだけでなく、心の辛さにも繋がり、治療にも影響をもたらします。これらがんによる痛みなどの苦痛により「自分らしく過ごせない」という辛さをできる限り軽減し、その人らしく過ごせるよう支援するのが、がん性疼痛看護認定看護師の役割です。患者さんやご家族の思いを大切にしながら、痛みを和らげるためどのような方法が効果的か、医師や薬剤師などとともに考え、患者さんやご家族が満足のゆく生活が送れるようにお手伝いしたいと思っています。
認知症看護認定看護師

本館6階病棟 川島 由賀子
2013年に認知症看護認定看護師の資格を取得しました。認知症で環境への適応がむずかしくなる、自分の思いを伝えることができなくなり入院されている患者が安全で、安心な生活が送れるようにするには環境を整えることが一番大事だと考えています。環境には私たち医療従事者も含まれます。そのため、認知症看護の知識を深め、チームで実践できる力を身につけることが必要です。そこで、認知症看護認定看護師の存在を知っていただくと共に、お互いに学びを深めていきたいと院内での勉強会や研修、今年度からは認知症ケアを語る会を通し、認知症看護を共に考え、行動できる仲間作りをしています。
認知症看護認定看護師となり、今の自分にできることは、「認知症患者のしぐさや言動には意味がある」を分析し看護に繋げるか「言葉にできない認知症患者の思いをくみ取る」ことの重要性を自分自身がモデルとなり示すことだと考えています。私たち医療従事者が認知症について理解を深め、適切なケアを行うことは認知症患者の安心につながります。そのために、スタッフと一緒に考え、笑顔になる看護を実践していきたいと思います。そして、「浅ノ川総合病院を選んで良かった」と認知症患者や家族に心から思っていただけるようなケアを目指したいと考えています。
認知症看護認定看護師

病棟所属 川倉 美紗季
~認知症の“人”との出会いを大切に~が私のモットーです。2020年に認知症看護認定看護師となり、現在は急性期病棟で勤務しています。
「自分が認知症になったらどうしよう」「大切な家族が認知症になったらどうしよう」と考えた事がある人もいるかもしれません。これまでの認知症のイメージは誤解されている事が多くありました。しかし今、認知症は誰にとっても身近なものになってきています。
認知症になっても、これまでと変わらずその人らしく過ごせるよう支援していくことが認知症看護認定看護師の役割です。認知症の人ができない事をすぐお手伝いするのではなく、認知症の“人”が持っている力を広げる事を大切にしています。特に慣れない入院生活ではお困りの事が色々出てくるかと思いますが、認知症の人に合わせて、安心してもらえるような声かけと対話を日々心掛けています。
がん放射線療法看護認定看護師

看護部 作田 憲一
がん放射線療法看護 認定看護師の役割は放射線治療を受ける患者さんの治療効果が最大限となるように治療完遂に向けサポートしていくことです。また副作用を予測し、症状を最小限に抑えられるように看護を行います。
当院ではノバリス、ガンマナイフと全身の病変に対応できる最高水準の放射線治療がおこなわれています。高齢社会では侵襲の少ない放射線治療を受ける患者さんは今後更に増加するといわれています。よって地域における当院の放射線治療を担う役割はより大きくなると考えられます
今後も更に患者さんが安心してより質の高い放射線治療を受けられるように、治療スタッフと協力し、治療前から治療後までしっかりとサポートしていきます。
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

看護部 柳 美知代
脳卒中リハビリテーション看護は、主に脳卒中患者を対象に重篤化の予防ケアを行うほか、機能障害を最小限に抑えるために早期からリハビリテーションを開始し、患者の持つセルフケア能力を高めることが大きな役割となっています。また患者の回復に向けて病棟看護師、リハビリスタッフが協働できるよう調整役として支援することも大切だと考えています。患者の持つセルフケア能力を評価し、急性期でどのようなリハビリが行われるかによって、その後の患者の回復が大きく左右されることを日々実感しています。急性期で可能な限りセルフケア能力を高め、回復期、生活期へと繋いでいけるよう邁進していきたいと思います。
摂食嚥下障害看護認定看護師

本館5階病棟 山本 政美
摂食嚥下障害看護認定看護師は、加齢や発達上の問題、疾病・治療により食べたり飲み込んだりする機能に障害をもつ人に対して、さまざまな場所で専門的で高度なケアが抵抗できることが求められます。その役割として摂食嚥下機能の評価および誤嚥性肺炎や窒息、栄養低下、脱水予防や適切かつ安全な摂食嚥下訓練の選択および実践があります。認定看護師として、自らケアの実践をするとともに、看護スタッフへの指導や相談に応じることも大きな役割の一つです。摂食嚥下障害患者の「食べる」権利を擁護し患者・家族の意思決定を尊重した看護が行えるよう目指しています。
特定行為研修修了看護師

あさのがわ訪問リハビリ・訪問看護ステーション 勢登 裕子
特定行為研修修了看護師は、認定看護師・専門看護師と異なり「資格」ではありませんが、「特定行為の研修を修了した看護師」を表しています。私は特定行為21区分の中から「創傷管理関連」と「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」の2区分を選択し、研修を修了したので、今まで医師しかできなかった「血流のない壊死組織切除」や「点滴」ができるようになります。在宅では寝たきりや家族の事情ですぐに治療できないことも多く、気が付いた時には状態が悪くなっていることや治癒するのに時間を要することが多いです。今は訪問先で療養者の皮膚の状態や栄養状態をアセスメントし、原因や誘因、改善や治癒方法を検討しています。今後は、この行為でもっと多くの人が安心して在宅で過ごせるよう、療養者や家族から信頼される看護師・訪問看護ステーションとして活動していきたいと考えています。
看護職員 就業環境
急性期一般入院料1(看護配置7対1)
労働環境:
夜勤体制は2交代・3交代を個人の希望により組合せています。また多様な勤務形態を組合せ、ゴールデンタイムと言われる早朝や夜21時までの職員配置を手厚くしています。 看護補助者の力を借り、看護職は看護中心に働いていくことができる環境を整えています。
保育所の設置により3歳未満児を預かり、夜勤ができる体制を整えてあります。
入院日数が短い分、上質の時間を提供できるスキルが培われます。瞬間瞬間に観察しアセスメントし、ケアする力をともに磨きましょう。
療養病棟
看護師・介護福祉士がほぼ同数同じ職場で働いています。夜勤は2名ずつ4名の体制をとっています。
療養病棟には看護の醍醐味があると信じています。じっくりと長い時間をかけて、その人の人生に寄り添いたい看護師はこの分野が最適でしょう。